
真冬の北海道で大盛り上がり!FOSS4G Hokkaido 参加レポート
この記事でわかること
- FOSS4G Hokkaidoのイベント概要
- QGISのハンズオンとセッションの内容
こんな人におすすめ
- 地域のFOSS4Gイベントについて知りたい方
- FOSS4GイベントにおけるQGISの発表内容に関心のある方
はじめに
「FOSS4G Hokkaido 2024」は、地理空間技術のオープンソースソフトウェア(FOSS4G)に関わる人々が集うカンファレンスイベントです。FOSS4G Hokkaido 実行委員会の主催により、2025年2月14日から15日にかけて北海道札幌市で開催されました。また、OpenStreetMap(OSM)のカンファレンスイベント「State of the Map Japan 2024」も同時開催されました。
この記事では、イベントの中からQGISに関連する話題を中心にピックアップしてレポートしていきます。
Day1:ハンズオンデイ
1日目は「ハンズオンデイ」として、FOSS4Gに関する4つの講座が開講されました。受講者は、QGISの基本操作、Svelte MapLibre GLを使用したWebGIS開発、R言語によるGIS処理など、実践的な内容を学びました。
ハンズオンでは、QGISによるデータ操作やシンプルなコードでのWebマップ作成を通じて、実践的な場面を想定しながらFOSS4Gツールを体験できました。
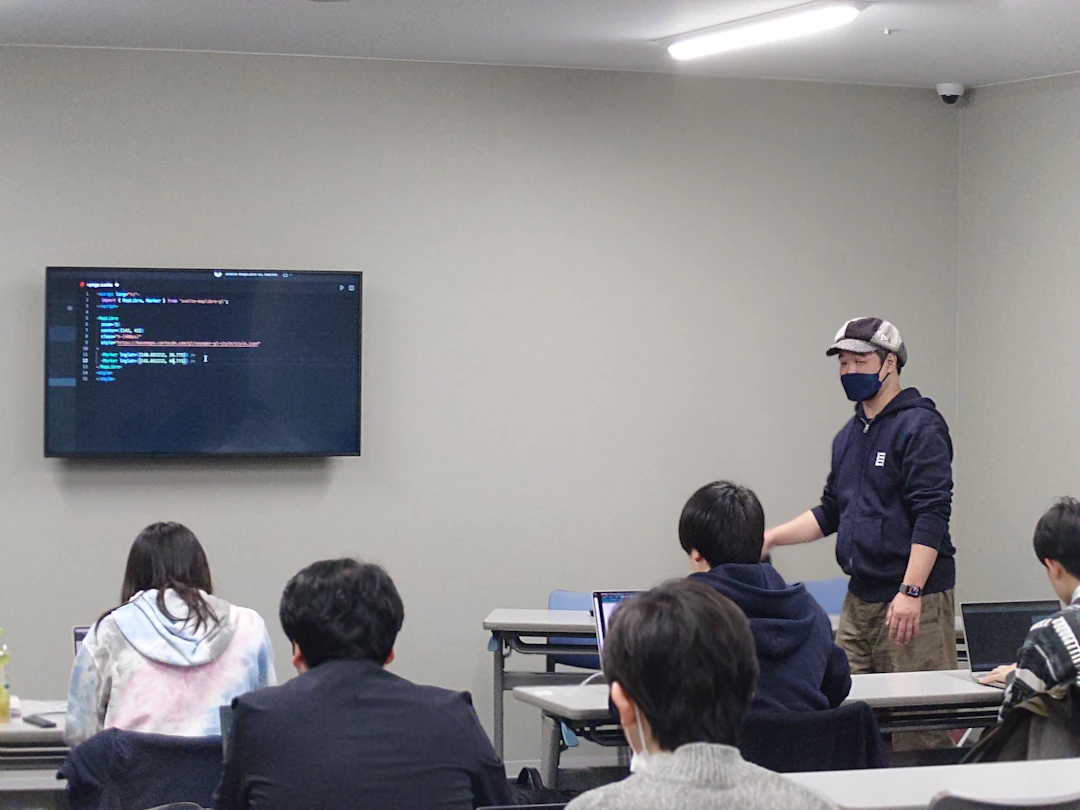
Day2:コアデイ
2日目は「コアデイ」として、FOSS4Gの利活用事例や開発事例の紹介、位置情報エンジニアとして働くことの魅力や可能性、海外のFOSS4Gイベントの参加レポートなど、多岐にわたるテーマで発表がありました。
以下では、QGISに関連する発表内容をご紹介します。
オープンデータを用いたQGISによる災害情報のReMappingについて

こちらは、北海道開発局 札幌開発建設部 河川整備保全課の村上さんによる発表です。
アメダスのデータのみを使用した雨量分布図では氾濫の履歴が十分に反映されなかったため、ダム、河川、行政区域などのデータを追加してQGISで新たな雨量分布図を作成したそうです。
また、震源地の分布を立体的に表現した3D震源分布図や津波浸水高分布図の作成例とその活用事例についても紹介がありました。
QGISを使い始めたきっかけは「きれいな雨量分布図を作りたい」という想いがあったからだそうです。地図をわかりやすくするため、川の名称などの地形情報を追加することで、閲覧者がより身近に感じられるよう工夫しているとのことでした。
FOSS4Gで実現するQGIS版Amazon Location Service Plugin

こちらは、株式会社MIERUNEの桐本さんによる発表です。
Amazon Location ServiceはAWSが提供する位置情報サービスです。ルーティングやジオコーディングなどの機能を備えており、これらの機能をQGISでも利用できるようにしたいという想いからこのプラグインを開発することにしたそうです。
プラグインをインストールしAmazon Location ServiceのAPIキーなどを設定すると、QGIS上で地図表示、ルーティング、ジオコーディングの各機能を利用できるようになります。マップキャンバス上でクリックするだけで地点のジオコーディングや、始点・終点を指定したルート検索が実行できるなど、直感的な操作性が印象的でした。
「Amazon Location Service」は、QGISの公式プラグインリポジトリで公開されており、どなたでも自由に利用できます。ただし、AWSアカウントの作成が必須であり、データの利用規約にも留意する必要があります。
GISを活用した音環境の可視化

こちらは、北海道大学 地域環境研究室の学生である萱沼さん、畑さん、林さんによる発表です。
「音環境の可視化」という発表タイトルのとおり、騒音予測、風車騒音、航空機騒音に関する研究成果が報告されました。
QGISプラグインを使用してパラメータから騒音レベルを計算し、また他の解析ソフトやツールの計算結果を地図上で分かりやすく可視化するなど、研究におけるQGISの具体的な活用事例が共有されました。また、航空機騒音予測モデルがQGISに実装されていないことに触れ、将来的にプラグインとして実装されることを期待しているとお話ししていました。
3名の学生が仲良く楽しそうに発表している姿が印象的でした。
TENGUNGUN:点群データハブとしてのQGIS活用
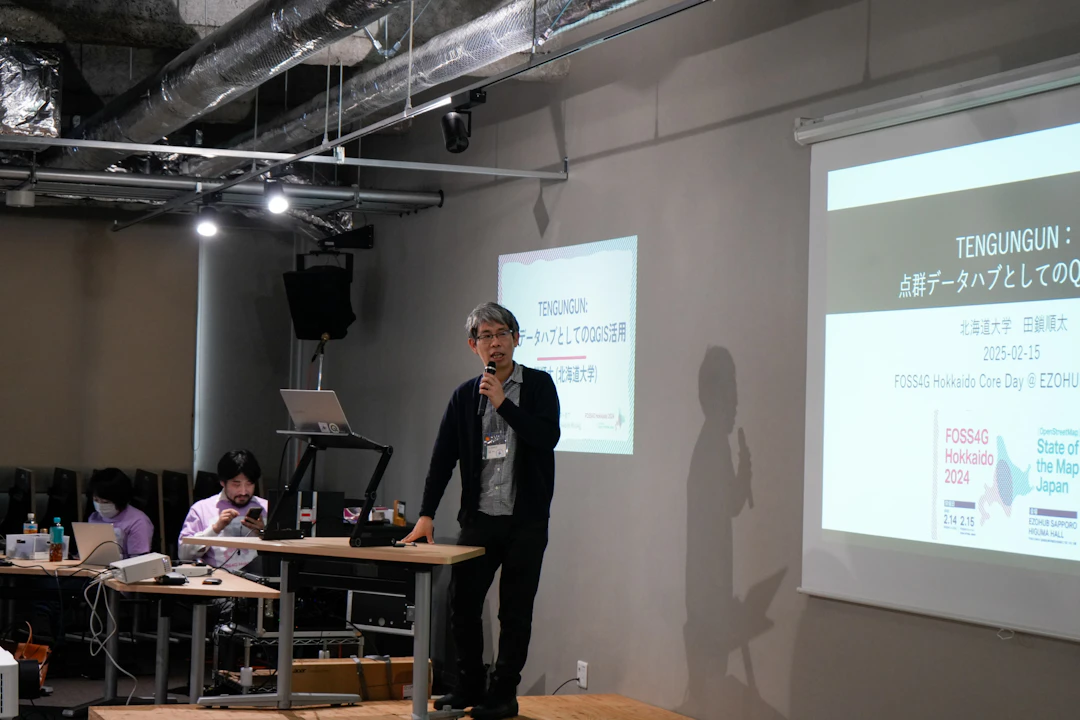
こちらは、北海道大学の田鎖さんによる発表です。
近年、多くの自治体が点群データを公開しており、これを他の情報と組み合わせて分析することで新たな知見が得られる可能性があります。しかし、データの提供方式はユーザーフレンドリーとは言いがたく、必要な地域の点群データを入手するには、該当する地域のメッシュを個別に選択してダウンロードする必要がありました。この課題を解決するため、点群データを効率的に取得できるQGISプラグイン「TENGUNGUN」の開発に至ったとのことです。
このプラグインは、QGIS上で選択した地域の点群データを特定してダウンロードできること、また、異なる自治体が提供するデータへの統一的なアクセス方法を実現することを目標に開発したそうです。
「TENGUNGUN」はQGISの公式プラグインリポジトリで公開されており、どなたでも自由に利用できます。
点群とSAMから建物情報を取得する
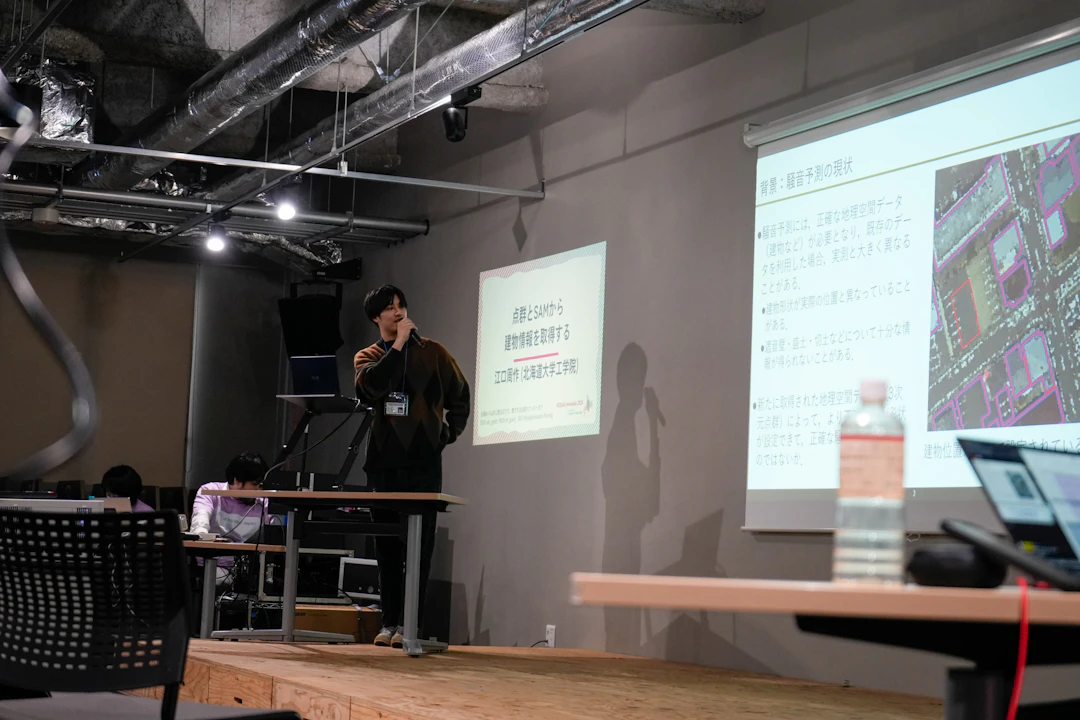
こちらは、北海道大学工学院の江口さんによる発表です。
騒音予測には建物などの地理空間データが必要ですが、既存データでは建物位置のずれや遮音壁、盛り土・切り土の情報不足があります。そのため予測値と実測値に差が生じますが、3次元点群データを活用することで、より正確な構造物情報に基づく高精度な予測が可能になると考えたそうです。
結果として、対象地域の建物を高精度で検出することができました。地域固有のパラメータを使用していないため、点群データが存在するどの地域でも適用できる可能性があるとのことでした。
FOSS4Gとオープンデータを使った一般教養科目「デジタルマッピング」
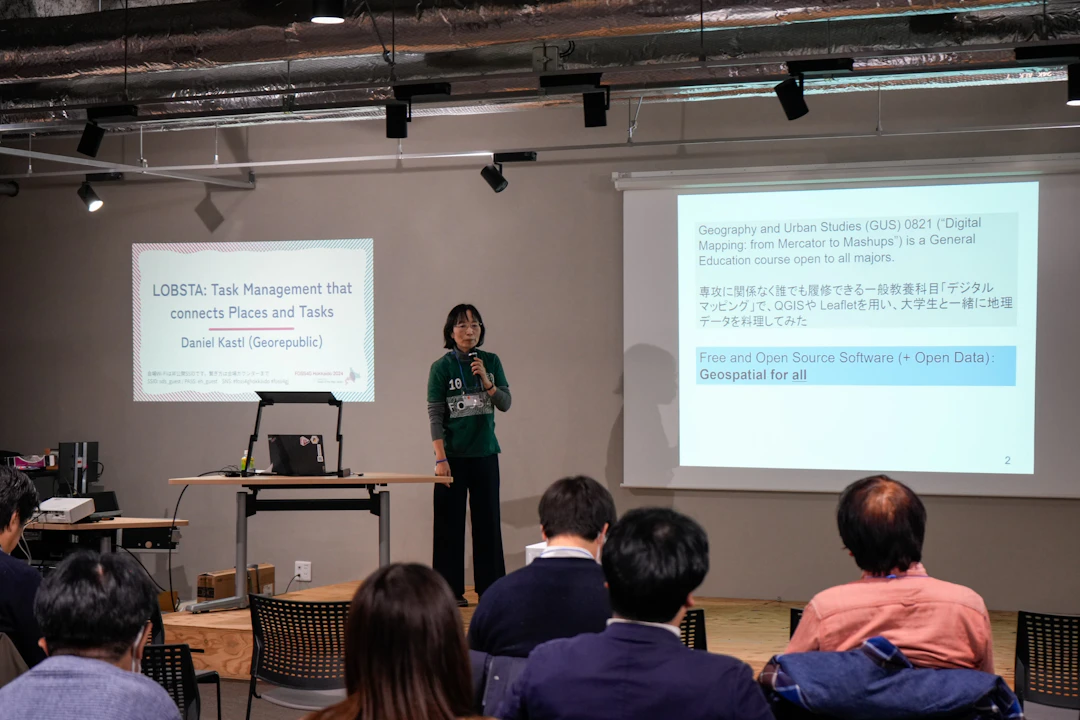
こちらは、国際基督教大学・テンプル大学日本校の小野さんによる発表です。
専攻を問わず履修可能な一般教養科目において、QGISやLeafletを活用した地理空間データの可視化の取り組みについて、教育現場でのFOSS4G活用事例として紹介されました。
QGISについては、大学周辺地域を題材に、シンボロジの変更やフィールド計算機の使用法などの基本操作を教えているそうです。今後は、バッファの作成やユニオンといった空間分析も講義に取り入れたいとのことでした。
専攻に関わらず地理空間技術に触れる機会があり、その中でQGISが教育ツールとして効果的に活用されている点が特に印象的でした。
おわりに
FOSS4G Hokkaido 2024では、地理空間技術の利用者や開発者が一堂に会し、幅広い情報共有が行われました。研究・教育現場での活用事例やプラグイン(拡張機能)の開発事例を通じて、QGISの活発な利用と開発の現状を知り、議論する貴重な機会となりました。
イベントの様子は、Youtubeで配信の録画を視聴することができます。
FOSS4Gイベントは世界各地で開催されており、最近では、FOSS4Gの国際カンファレンスイベントである「FOSS4G Global」が2026年に広島県で開催されることが決定しました。
QGISをはじめとするFOSS4Gに興味をお持ちの方は、ぜひ他のイベントにも参加してみてください。
FOSS4Gイベント参加レポートはこちら


QGIS LABは、オープンソースのGISソフトウェア「QGIS」に関する総合情報メディアです。「位置から、価値へ。」をコンセプトに、位置情報で世界を拓くための知識と技術をお届けします。